【参考文献】
・バートン・ホブソン『世界の歴史的金貨』泰星スタンプ・コイン 1988年
・久光重平著『西洋貨幣史 上』国書刊行会 1995年
・平木啓一著『新・世界貨幣大辞典』PHP研究所 2010年
こんにちは。
6月も終わりに近づいていますが、まだ梅雨空は続く模様です。蒸し暑い日も増え、夏本番ももうすぐです。
今年も既に半分が過ぎ、昨年から延期されていたオリンピック・パラリンピックもいよいよ開催されます。時が経つのは本当にあっという間ですね。
コロナと暑さに気をつけて、今年の夏も乗り切っていきましょう。
今回はローマ~ビザンチンで発行された「ソリドゥス金貨」をご紹介します。
ソリドゥス金貨(またはソリダス金貨)はおよそ4.4g、サイズ20mmほどの薄い金貨です。薄手ながらもほぼ純金で造られていたため、地中海世界を中心とした広い地域で流通しました。
312年、当時の皇帝コンスタンティヌス1世は経済的統一を実現するため、強権をふるって貨幣改革を行いました。従来発行されていたアウレウス金貨やアントニニアヌス銀貨、デナリウス銀貨はインフレーションの進行によって量目・純度ともに劣化し、経済に悪影響を及ぼしていました。この時代には兵士への給与すら現物支給であり、貨幣経済への信頼が国家レベルで失墜していた実態が窺えます。
コンスタンティヌスはこの状況を改善するため、新通貨である「ソリドゥス金貨」を発行したのです。
コンスタンティヌス1世のソリドゥス金貨
表面にはコンスタンティヌス1世の横顔肖像、裏面には勝利の女神ウィクトリアとクピドーが表現されています。薄手のコインながら極印の彫刻は非常に細かく、彫金技術の高さが窺えます。なお、裏面の構図は18世紀末~19世紀に発行されたフランスのコインの意匠に影響を与えました。
左:フランス 24リーヴル金貨(1793年)
ソリドゥス(Solidus)はラテン語で「厚い」「強固」「完全」「確実」などの意味を持ち、この金貨が信頼に足る通貨であることを強調しています。その名の通り、ソリドゥスは従来のアウレウス金貨と比べると軽量化された反面、金の純度を高く設定していました。
コンスタンティヌスの改革は金貨を主軸とする貨幣経済を確立することを目標にしていました。そのため、新金貨ソリドゥスは大量に発行され、帝国の隅々に行き渡らせる必要がありました。大量の金を確保するため、金鉱山の開発や各種新税の設立、神殿財産の没収などが大々的に行われ、ローマと新首都コンスタンティノポリスの造幣所に金が集められました。
こうして大量に製造・発行されたソリドゥス金貨はまず兵士へのボーナスや給与として、続いて官吏への給与として支払われ、流通市場に投入されました。さらに納税もソリドゥス金貨で支払われたことにより、国庫の支出・収入は金貨によって循環するようになりました。後に兵士が「ソリドゥスを得る者」としてSoldier(ソルジャー)と呼ばれる由縁になったとさえ云われています。
この後、ソリドゥス金貨はビザンチン(東ローマ)帝国の時代まで700年以上に亘って発行され続け、高い品質と供給量を維持して地中海世界の経済を支えました。コンスタンティヌスが実施した通貨改革は大成功だったといえるでしょう。
なお、同時に発行され始めたシリカ銀貨は供給量が少なく、フォリス貨は材質が低品位銀から銅、青銅へと変わって濫発されるなどし、通用価値を長く保つことはできませんでした。
ウァレンティニアヌス1世 (367年)
テオドシウス帝 (338年-392年)
↓ローマ帝国の東西分裂
※テオドシウス帝の二人の息子であるアルカディウスとホノリウスは、それぞれ帝国の東西を継承しましたが、当初はひとつの帝国を兄弟で分担統治しているという建前でした。したがって同じ造幣所で、兄弟それぞれの名においてコインが製造されていました。
アルカディウス帝 (395年-402年)
ホノリウス帝 (395年-402年)
↓ビザンチン帝国
※西ローマ帝国が滅亡すると、ソリドゥス金貨の発行は東ローマ帝国(ビザンチン帝国)の首都コンスタンティノポリスが主要生産地となりました。かつての西ローマ帝国領では金貨が発行されなくなったため、ビザンチン帝国からもたらされたソリドゥス金貨が重宝されました。それらはビザンチンの金貨として「ベザント金貨」とも称されました。
アナスタシウス1世 (507年-518年)
ユスティニアヌス1世 (545年-565年)
フォカス帝 (602年-610年)
ヘラクレイオス1世&コンスタンティノス (629年-632年)
コンスタンス2世 (651年-654年)
コンスタンティノス7世&ロマノス2世 (950年-955年)
決済として使用されるばかりではなく、資産保全として甕や壺に貯蔵され、後世になって発見される例は昔から多く、近年もイタリアやイスラエルなどで出土例があります。しかし純度が高く薄い金貨だったため、穴を開けたり一部を切り取るなど、加工されたものも多く出土しています。また流通期間が長いと、細かいデザインが摩滅しやすいという弱点もあります。そのため流通痕跡や加工跡がほとんどなく、デザインが細部まで明瞭に残されているものは大変貴重です。
ソリドゥス金貨は古代ギリシャのスターテル金貨やローマのアウレウス金貨と比べて発行年代が新しく、現存数も多い入手しやすい古代金貨でした。しかし近年の投機傾向によってスターテル金貨、アウレウス金貨が入手しづらくなると、比較的入手しやすいソリドゥス金貨が注目されるようになり、オークションでの落札価格も徐々に上昇しています。
今後の世界的な経済状況、金相場やアンティークコイン市場の動向にも左右される注目の金貨になりつつあり、かつての「中世のドル」が今もなお影響力を有しているようです。
【参考文献】
・バートン・ホブソン『世界の歴史的金貨』泰星スタンプ・コイン 1988年
・久光重平著『西洋貨幣史 上』国書刊行会 1995年
・平木啓一著『新・世界貨幣大辞典』PHP研究所 2010年
投稿情報: 17:54 カテゴリー: Ⅱ コイン&コインジュエリー, Ⅳ ローマ | 個別ページ | コメント (0)
こんにちは。
最近は更新がすっかり疎かになっておりました。
本日は古代コインから少しだけ離れて、現在使用されているコインに関してご紹介します。
皆さんは普段使っているコインの縁(ふち)を気にしたことはありますか? コインの世界では、ふちのことを「Edge(エッジ)」と呼びます。エッジはコインの流通状況や、これまでの持ち主の保管状況が垣間見えます。
記念コインなどではない小さなコインは、人の手から手へ渡すときになどに落としてしまうことがありますが、造幣局で造られてすぐに袋に入れられたとき、コイン同士があたって傷がつくこともあります。
もちろん、財布の中に他のコインがたくさん入っていたり、金融機関やコイン商、コレクターが同じ種類のコインを一箇所にまとめて置くなどすると、コイン同士が当ってしまいます。コインのエッジは、文字通りコインの端っこですから、そのような状況では傷がつきやすくなります。
また、紙で挟むタイプのコインホルダーに入れておくと、面の部分は傷がつかず美しく保たれますが、隙間から空気が入るのでエッジの部分だけ酸化して変色している・・・なんてことも見受けられます。円形である以上、変形させた箇所では金属に圧がかけられているため、変色が起こりやすいのです。
コインが円形であるのは、落としたときに破損しにくいから、とよく云われます。確かに、紀元前6世紀の古代ギリシャから2500年以上を経た現在に至るまで、お金の形は「円」がスタンダードです。もちろん四角形や五角形、六角形の流通用コインも多く発行されてきましたが、自動販売機が普及した現在では、むしろ円形であるほうが効率が良いとされます。
ただ、コインの素材に貴金属が使用されていた時代、コインのエッジ部分が削り取られてしまう事件も多かったようです。つまり、一枚のコインのふち部分を少しだけ削り取れば、わずかな金(または銀)を得られ、コインそのものは額面通りに使用してしまうわけです。一枚から取れる分量はほんの僅かでも、100枚、1000枚から採っていけば莫大な価値になります。
そうした変造を防止するために、コインの発行者はエッジに細工を施しました。いわゆる「ギザ十円玉」のように、エッジ部分がギザギザになっているのはその名残なのです。
紀元前2世紀~紀元前1世紀頃の古代ローマでは、コインのエッジにキザが入れられたものが発行されていました。しかし、このコインはイレギュラーなものであったようで、ある特定の年に発行されたものに限られていたようです。
偽造防止の観点からみれば大変有効に思えますが、結果的にローマでは共和政時代、帝政時代を通してギザ有りコインが定着することはありませんでした。
当時のローマでは貨幣発行担当者が毎年変わっており、その都度コインのデザインは担当官の意向に任されていたこと、また一つ一つ手作業でギザを入れるため、余計な手間が増えて大量生産には不向きであったこと等が原因として考えられます。
しかし近代に入り、大型銀貨の登場や機械によるコインの大量生産が普及すると、エッジにギザを入れることが一般化します。それは高額面ほど顕著であり、やがて装飾や文字を入れるなど凝ったものも登場しました。
ここからはタイプ別にエッジを紹介します。
全く何も施されていない、最もシンプルなエッジ。主に低額面のコイン(青銅貨など)にみられます。
Plain(プレーン)エッジ、またはSmoothエッジと呼ばれます。
現在、日本では1円玉、5円玉、10円玉にみられるタイプです。
いわゆる「ギザ」タイプ。近代から現代に至るまで、幅広いコインに見られるエッジタイプ。
Reeded(リーディッドエッジ)、またはMilled(ミルドエッジ)と呼ばれます。
シンプルにギザが並んでいますが、溝と溝の間が狭く細かいため、容易に変造は出来ません。
現在では50円玉と100円玉、旧10円玉にみられます。旧10円玉は、似たサイズの100円玉の登場により、周囲のギザを削られプレーンエッジになりました。
現在の500円玉にもギザが入っていますが、よく見ると斜めになっているのがわかります。これは「Slant-Reeded」と呼ばれ、偽造防止には大変有効です。
Reeded(ギザ)の入ったエッジの真中に一本の溝を入れ、その中にさらに細かい細工を施したタイプ。
主に第二次世界戦中~後、銀をコインに使用できなくなったイギリス植民地で多く見られました。写真のコインも第二次世界大戦中の英領インド銀貨ですが、銀含有率は50%です。含有率の下がった銀貨の価値と信用を少しでも維持するために施された偽造防止措置と考えられます。
文字や銘文が表現されたもの。主に20世紀初頭までの大型銀貨や、金貨に見られました。特にヨーロッパ諸国においては顕著であり、ターレル銀貨やクラウンサイズのコインには、モットーや額面、発行年、ミントマークといった銘が刻まれました。
陰刻から陽刻まで幅広い分類がありますが、近年の記念コインには主に陰刻で打たれることが多いようです。エッジに刻まれた銘は見落とされることが多いのですが、大変意味深な興味深い文が刻まれていることもあり、ひっそりと隠されていた様々な発見もあります。
また珍しいものとしては、18世紀~19世紀のポルトガル金貨のように、魚のうろこ状になっているものもあります。薄手の金貨であるが故に、このような細工がされたと考えられます。
現在、世界各国で発行されているコインの多くに「ギザ」や、その他の加工が施されています。今では貴金属を流通用コインに用いることは無くなったため、変造防止というよりも、ほとんど形式的なものに成っています。
しかし現在では視覚に障害のある人が、似たサイズでも異なる額面のコインを触って区別できるように、ギザギザが残され、役に立っています。
皆様もお手持ちの財布に入っているコイン、または御自身のコインコレクションのエッジを一度ゆっくりと眺めてみて下さい。見落としていた、面白い発見があるかもしれませんよ。
こんにちは。
だんだんと春らしくなってきました。まだ強風と乾燥は続いていますが、日差しが暖かく感じる日も多くなってきています。
さて、最近ブログのほうをすっかり疎かにしておりますが、忘れないうちに何かしら更新していきたいと思います。
今回は、昨今のローマコイン市場に関して。
前回もご紹介しましたが、最近は世界的なコイン投資の広まりによって、古代ギリシャ・ローマコインの品薄・値上がりが進んでいます。
特にアメリカのコイン市場が顕著なのですが、古代コインの供給地であるヨーロッパの情勢も変わりつつあるようです。
これにはユーロ危機以降、ギリシャやイタリアからの古代出土品の移動が、厳しく制限されはじめていることも背景に有るようです。
これまで、イタリアやギリシャの遺跡から出土したコインや芸術品は、アンダーグラウンドにドイツ、フランス、イギリス、アメリカなどの大手市場に流されることがあり、一つの重要な供給源にもなっていたのです。
しかし、アメリカやEUでは歴史的遺物を保護する動きが政府レベルで進められ、その重要性が取り上げられるようになりました。特にEUでは、たとえ域内であっても入手ルートがはっきりと分かるものでなければ出土国へ返還するべきとして、取り締まりも厳しくなっています。ギリシャもイタリアも経済的に厳しい状態が続いている為、自国の歴史的遺産を水面下で動かされることに敏感になっているのかもしれません。
この両国は財政難から自分達で徹底的取締りを出来なくとも、EUに働きかけて加盟国各国に取り締まりを求めることはできます。
その為、古代コインをはじめとする古代芸術品の水面下での供給は一気に萎えてしまい、現在の品不足を招いたのでは、との見方もされています。
しかし、激しい内戦状態が続くシリアやイラクなどからは、トルコを経由して古代のコイン(パルティアやフェニキア、ローマ帝国属州時代のもの)や、その他の出土品が今後大量流出する可能性もあります。コインの市況は、激動する国際情勢に大きく左右されているといえるでしょう。
このところそうした品薄の情勢を象徴しているのが「ローマ神のデナリウス銀貨」です。
このローマ神は、都市国家ローマの守護女神とされ、ローマ市そのものを象徴する神でした。
翼付き兜を被った勇ましい姿で表現されるのが常でしたが、イヤリングやネックレスなどの装飾品も身に付けており、女性らしさも併せ持った美女神として表現されました。
共和政時代のローマでは、このローマ神を表現したデナリウス銀貨が100年以上の長きにわたって造られ続けました。尚、左下に刻まれた「X」の銘は、当時のデナリウス銀貨1枚がアス銅貨10枚に相当したことを示しています。もともと「デナリウス」の呼称は、「10」の形容詞からとられた貨幣単位でした。
紀元前2世紀後半にアス銅貨10枚⇒16枚へ改正されてもこの「デナリウス」の呼称は残り、ローマ帝国が滅ぶ直前まで、長らくローマの基軸通貨単位でした。(※X銘からXVIの銘に変更されたローマ神コインもみられます)
さて、長く発行され続けたローマ神のコインは、時の通貨発行責任者の意向で裏面が変更されたことでバリエーションに富みますが、特異で興味深いものを除けば、現存数が多い、手に入れやすいありふれた古代ローマコインとして人気がありました。
ところが、最近はこのローマコインを見かける機会が減り、海外オークションの出品数も以前と比べて減少しているように感じます。無論、入札参加者は増えても出品数が少ないのですから、出品されたローマ神のコインの値段はどんどん上がってしまいます。
こうした状況は、ユリウス・カエサルの軍団が発行した「象コイン」に似ています。このコインは短期間に発行されたものとはいえ、現存数が多く、よく見かけられたコインだったはずですが、近年は常に高値で取引されるコインになってしまいました。
しかしローマ神のコインは、初めて古代ローマのコインを買われる方が、最初に手にすることの多い代表的ローマコインです。毎回オークションでは入札しているのですが、その度に高値で落札されてしまい、なかなか入荷し難たくなっているのが現状です。
ローマコインは本来、大型の銀貨があまりなく、基軸とされたのは直径20mm前後、重さ3g前後の小さなデナリウス銀貨でした。
従来、デナリウス銀貨は発行の歴史が長く、バリエーションと現存数が豊富であることから、数を揃えて楽しむことが出来ました。(ガルバやオットー、ペルティナクスなど、在位3ヶ月程の短命皇帝は除きます。)
その為、長いローマ史を手にとって観賞できる、手軽な古代遺物として愛されたのです。
アウレウス金貨やソリダス金貨は、絶対数が限られていて、かつ人気があって昔から高価でした。
逆に、セステルティウス銅貨は発行数は格段に多い分、卑金属のため2000年近い経年変化に耐えられないこと、一般市民の生活の中で広く流通したことで退蔵されず、磨耗や消費が盛んに行われたため、美しく残っているものは特に高値で取引されました。
しかし、エジプト属州やシリア属州で発行された大型のテトラドラクマ銀貨(※ギリシャ系地域に合わせてドラクマ幣制を採用。Billonと呼ばれる低品位銀で造られた。)や、カラカラ帝以降、軍人皇帝時代に盛んに発行されたアントニニアヌス貨(※デナリウス2枚に相当するとされたが、実際には銅貨に銀メッキを施した粗悪なコインだった。デナリウスと異なり直径が大きく、皇帝は光の冠を戴いている。)は、比較的安価に取引され、現在でもその傾向はあまり変わっていないように思われます。
またデナリウス銀貨であっても、五賢帝時代以降、つまりセウェルス朝時代(2世紀末~3世紀前半)のコインは状態が良好で素晴らしいものが多いのですが、やはり絶対数が多いためなのか、オークションでも比較的安く手に入るように思います。
欲しいときにいつでも、好きなタイミングで入荷できるコインであった「ローマ神のデナリウス」は、今やある時に入荷しておかねばならないコインに出世してしまったようです。時勢の急激な変化を感じざるを得ません。
こうした古代ギリシャ・ローマコインへの過熱は何時まで続くのか、これからも情勢を見守っていきたいと思います。
すっかりご無沙汰しておりました。
はやくも1月が終わり、2月に入りました。
しかし寒さ、北風はますます厳しくなっていますね。
2月に入り、ここ最近のコイン情勢をごく簡単に書き連ねたいと思います。
ここ数年、世界的に投資目的のコイン需要が高まっているせいもあってか、コインの高値が続いています。資産運用の意味もあって、金に投資する一般の方も多く、地金価格自体が上がっていることも大きな要因ですが、近代の大型金貨はもとより、古代ギリシャ・ローマ、中世イタリアの金貨、銀貨まで上がっています。
2年~3年前の海外コインオークションカタログを読み直すと、今から考えればとても安かったなぁ、と溜息をついてしまうほどです。
例えば古代ローマコインでは、カエサル (CAESAR)の名前が入った有名なデナリウス銀貨 (蛇を踏む巨象/四種の神器)は、数年前までは数枚でいくら、という風に量り売りのような形で出品されていることもありましたが、今では状態の優れたものならば1枚2000ドル近い値段で取引されています。
古代ギリシャ時代、レスボス島などで発行されていた超小型のエレクトラム貨まで、現在ではかつての1.5倍~2倍の価格になってしまいました。
このような状況は、ヨーロッパでのユーロ不信が関わっています。
先日のギリシャでの選挙結果や、欧州中央銀行の量的緩和観測などで、通貨ユーロへの信用は大きく揺らぎました。先月のスイスフラン暴騰も、周辺の国々が使うユーロに対して、人々が信頼を置いていないことの表れでしょう。
その為、ヨーロッパでは「現金=ユーロ」を「モノ」に代えておきたいという需要の高まりから、付加価値・資産性の高い骨董品や、宝飾品が注目されているのです。
その流れの中で、比較的小さくて保管しやすく、それでいて芸術性や歴史も楽しめる「コイン」が多く買われているようです。
日々海外のオークションをチェックして感じることは、古代、中世、近現代、金貨、銀貨、銅貨も関係なく、全ての種類のコインが、数年前と比べて上がっているということです。
オークション運営会社も、需要の高まりを見越して強気になっているのか、スタート値を高く設定したり、手数料の割合を引き上げたりしているのも見受けられます。これには昨今の円安も加わって、仕入には大きなダメージになります。
ただ、価格面以上に危機感を抱いているのは、「高くなった」という以上に「モノがなくなった」ということです。
今年1月にニューヨークで開かれたコインオークション・コインショーには、例年通り多くの業者もやってきましたが、各ブースには大型金貨が品薄の状態で、買えるものは殆ど無かったといわれています。
また、ロンドンやパリのコイン業者でも、古代コインで状態の良い物はどんどん無くなっているようですし、オークションサイトを見ても、状態の悪いものが増えているように感じます。
そもそも数に限りがあるものですから、買う人が増えれば増えるほど値段も上がっていくのが自然です。
しかし近年はただコインが好き、古いものや歴史に興味があるという人に限らず、資産運用の目的でコインを集める人が増えたことにより、従来とは異なった流れが生み出されているようです。
この流れがいつまで続くのかは分かりませんが、今年も高値・品薄の状態は続くのではないかと考えられます。昔からのコイン収集家にとって、厳しい情勢はしばらく続くでしょう。
投稿情報: 15:57 カテゴリー: Ⅰ 談話室, Ⅱ コイン&コインジュエリー, Ⅶ えとせとら | 個別ページ | コメント (1)
こんにちは。
本日は古代ギリシャのコインをご紹介します。
今回は、アレキサンダー大王による征服後、エジプトを支配した「プトレマイオス朝」のコインに関する記事です。

特徴的な彼の顔つきは、コインの上にリアルに、そして2世紀以上の長きに亘って刻まれることになった。
プトレマイオス朝以前からエジプトには、ファラオを頂点とする高度な文明社会が栄えていました。ギザのピラミッド建設に代表されるように、高度な建築技術や数学知識を古くから有した国であり、また古代エジプト神話に基づく神権政治が数世紀に亘って続けられていたのです。
しかしピラミッドが建設された頃、または少年王ツタンカーメンが健在であった時代には、エジプトには「コイン」といった貨幣は存在しませんでした。古代エジプトは高度な文明社会を形成していましたが、経済的には麦といった食糧や、貴金属製品などを介した物々交換が基本となっていたのです。

紀元前2500年前後に建設されたとされる。数十年以上の年月をかけ、膨大な労働力が費やされた。
古代エジプトで、現在の我々がイメージする「コイン」を造り始めたのは、古代エジプト史でいえば末の末、最後の王朝となったプトレマイオス朝の時代になってからでした。このプトレマイオス朝は、ギリシャ系マケドニア人が建設した外来の王朝でした。プトレマイオスは、ギリシャの「ドラクマ」を基準とする通貨制度を持ち込み、ギリシャ式のコインをエジプトで造幣・発行しました。このことからプトレマイオス王朝がエジプトで造ったコインは、広い意味での「ギリシャコイン」に含まれます。
プトレマイオス朝を興したのは、かのアレクサンドロス3世(アレキサンダー大王)の腹心将軍の一人であったプトレマイオス1世ソーテール(BC367年~BC282年)です。なお、「ソーテール」とはプトレマイオスに付けられた尊称であり、「救済者」の意味です。
プトレマイオスはアレクサンドロスが幼少の頃よりの友人であり、よく行動を共にして信頼関係を深めたと云われます。プトレマイオスはアレクサンドロスによる東方遠征にも同行し、大王と呼ばれた友をよく補佐しました。伝統的にマケドニアの王と将軍達の関係は、厳格な臣従関係というよりも「信頼できる友人」という間柄に近かったとされています。王と将軍達は、主君・部下の関係でありながら友情関係で結ばれており、戦場でも行動を共にする「戦友」の関係でもありました。
マケドニア軍がギリシャ全土を席巻し、東方の大国ペルシアをも倒す軍事力を養えたのは、この信頼関係が大きな役割を果たしたと云われています。それは、当時のギリシャの市民参加型民主政治とも、エジプト、ペルシアの絶対君主制・神権政治とも異なるものでした。
BC323年にアレクサンドロス大王が亡くなると、プトレマイオスはエジプトのサトラップ(総督)となりました。やがて大王の遺した巨大すぎる帝国を巡り、「後継者(ディアドコイ)戦争」が勃発します。かつて、大王の下で共に戦った将軍達が、敵同士となって勢力圏争いを繰り広げ、やがて各地で独自の王朝を打ち立てるようになったのです。
プトレマイオスはBC305年から「プトレマイオス1世」としてエジプトのファラオ(王)となり、そこから「プトレマイオス朝エジプト」の歴史が始まったととらえられています。このプトレマイオス朝エジプトは、BC30年にクレオパトラ女王(クレオパトラ7世)の自決によって滅亡するまで、およそ270年近く続きました。
プトレマイオス1世が「ファラオ」を称したのにも分かるように、彼はエジプトの伝統や社会を尊重し、現地の風俗を王朝にも取り入れました。外来のギリシャ人によって建設された王朝でしたが、自分達の文化を一方的に押し付けることなく、上手く溶け込もうと努力したことが功を奏し、王朝が長く繁栄する基礎を築いたのです。

また、プトレマイオスは武勇だけでなく学問にも優れた統治者でした。王朝の首都となったアレクサンドリア(アレクサンドロス大王の名に因んだ都市)には、当時、世界最大の図書館を建設し、地中海世界の知識を多く収蔵しました。そのためアレクサンドリアには、ギリシャなどからも学者や学生が多く集まる学問都市として栄えました。商業にも栄えた貿易都市であったアレクサンドリアは、地中海各地から来航する大型商船によって、富や産物、人以外にも「情報」が齎されました。それらは学者達によって「知識」として書物に記され、巨大な図書館に集積されたのです。
図書館に併設された「ムセイオン」と呼ばれる学問研修施設は、当時の地中海世界随一の「学問の殿堂」として広く知られ、後に英語の「ミュージアム」の語源となりました。
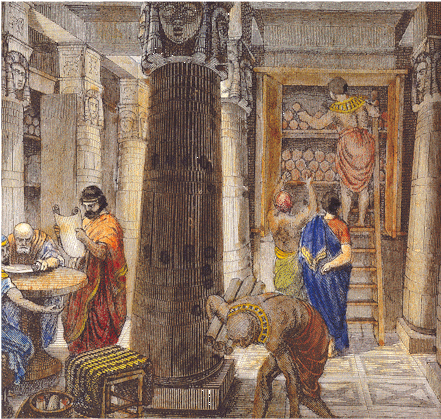
エジプトの統治と基盤づくりに力を入れたプトレマイオスはBC282年に亡くなりました。彼はアレクサンドロス大王の「後継者」たちの中で雄一、自らのベッドの中で息を引き取った人物でした。他の後継者が戦いに明け暮れ、戦場で命を落としてゆく中、プトレマイオスの最期は安らかなものだったのです。
プトレマイオス1世亡き後のプトレマイオス朝は、ギリシャ人(マケドニア人)の血統を「高貴な王家の血筋」として保とうとし、エジプト人の血を加えることは極力避けました。これも、古代から続くエジプト歴代王朝に倣ったものと考えられていますが、その結果としてプトレマイオス朝は古代エジプトの諸王家と同じく兄弟婚・近親婚を繰り返しました。
プトレマイオス朝最後のファラオとなったクレオパトラ7世女王は、イメージでは褐色の妖しげなオリエンタル風味漂う美女として描かれていますが、実際の記録ではギリシャ人と同じく白い肌であったと伝えられています。プトレマイオスの出身地、マケドニアの血筋は、250年を経ても保たれ続けていたのです。
プトレマイオス朝はギリシャ系の血を保ちつつ、セレウコス朝シリアなど周辺諸国の王朝と政略結婚も行いながら国家の基盤を安定させましたが、勢力を地中海全域に拡大させていたローマの力には敵わず、BC30年以降、エジプトはローマの一属州となり、東地中海の大国としての歴史を終えたのです。
さて、プトレマイオス朝で発行されたコインは、代表的なものとして「プトレマイオス1世」の肖像が打たれたコインがよく知られるところです。
プトレマイオス1世は総督時代にもコインを発行しましたが、それらは主君であるアレクサンドロス大王の神格化された肖像が打たれたものでした。しかしファラオに即位した後は、自らの肖像をコイン上に打たせることになるのです。
象の皮を被った大王が打たれた銀貨は、総督時代のプトレマイオスが統治したエジプトで発行された。一般的な「獅子の皮」に代わった亜種として知られるが、希少性が高い一枚として知られている。
当時のギリシャ本土では、生存する実在の王が、自らの肖像をコイン上に表現させることはほとんど例がありませんでした。しかしアレクサンドロス大王とその父フィリッポス2世は、自らの肖像を「ギリシャ神話の神」として打たせ、慣例を打ち破ったのです。
プトレマイオスはさらに伸張させ、神としてではなく「ファラオ」としての自らの姿をコイン上に表現しました。これは、ファラオは「神」に近しい存在と考える、現地のエジプト人の考え方にはよく合ったものでした。プトレマイオスはエジプトとギリシャ、両方の文化・価値観を巧みに融合させ、新しい形のコインを発行するに至ったのでした。
興味深いことに、プトレマイオス1世の肖像は、本人が死去して以降も長くコイン表面に打たれ続けました。若干の例外もありますが、その慣習は王朝の滅亡まで続けられたのです。
テトラドラクマ銀貨 プトレマイオス1世ソーテール/ゼウスの大鷲
この時代より、プトレマイオス自身の肖像が刻まれる。裏面の大鷲の左側には、発行者である「プトレマイオス」の名がギリシャ文字で刻まれている。そのことから現地エジプトでの流通に重きをおかず、むしろ地中海沿岸のギリシャ系諸国との交易決済用に多く造られた銀貨とも考えられる。首都アレクサンドリアで発行された。
テトラドラクマ銀貨 プトレマイオス1世ソーテール/ゼウスの大鷲
プトレマイオス1世亡き後を継いだ、プトレマイオス2世時代のテトラドラクマ銀貨。しかし表面には先代と同じく、プトレマイオス1世の肖像が打たれた。この慣習は引き継がれ、王朝末期まで続いた。
裏面には稲妻を掴んだ大鷲が表現されている。この大鷲はギリシャ神話の最高神ゼウスの聖鳥であり、エジプトにおけるプトレマイオス王朝の権威を示すものとされている。
尚、プトレマイオス2世はコイン収集家としても知られている。かつて商業・学問の都として繁栄したアレクサンドリアには地中海沿岸各地から富と人、文物が集まり、その流れに乗って各地の多種多様なコインも集まったことだろう。その恵まれた環境が、ファラオのコインコレクションを充実させるのに大いに役立ったと推測できる。
テトラドラクマ銀貨 プトレマイオス1世ソーテール/ゼウスの大鷲
プトレマイオス朝時代中期の発行貨。コイン全体の彫りや造形に変化がみられる。
テトラドラクマ銀貨 プトレマイオス1世ソーテール/ゼウスの大鷲
プトレマイオス朝時代末期の発行。アレクサンドリアの造幣所で造られたが、銀の品位は低下し、明らかに造形のレベルも落ちていることがわかる。当時のエジプトは伸張するローマの前になすすべも無く、内政の混乱によって国内は不安定であった。
なお、プトレマイオス12世はクレオパトラ7世女王の父親であり、このコインはクレオパトラが少女の時代に発行されたものである。
ペントオボル銅貨 ゼウス神/ゼウスの大鷲
またプトレマイオス朝時代のエジプトでは、見事な大型銅貨が多数発行されたことでも知られる。このペントオボル銅貨は45g以上ある。
尚、プトレマイオス朝時代の最後を華々しく飾った女王といえば、クレオパトラ女王ですが、彼女の時代にもコインは発行されました。しかし、彼女の肖像が表現されたコインは基本的に小型の銅貨であり、現存するもののほとんどは状態が良くありません。状態が悪くとも、コインの市場では高値で取引されています。
コインにかろうじて表現された絶世の美女王 クレオパトラは、輪郭もぼやけ、はっきりしない肖像ですが、明らかにギリシャ人風の高貴な女性として表現されています。コインは往時の彼女の美貌を知るうえでの、貴重な史料でもあるのです。

囚人で毒を試すクレオパトラ7世女王 (1887年 アレクサンドル・カバネル)
お読み頂き、ありがとうございます。
次回も宜しくお願いいたします。
こんにちは。
本日は古代ローマ帝国のコインをご紹介します。
今回は五賢帝の一人として名高いアントニヌス・ピウス帝の時代に発行されたコインです。

アントニヌス・ピウス帝の「ピウス」とは、「敬虔者」「慈悲深き者」の意味であり、皇帝即位後に元老院から授けられた称号です。後世、カラカラ帝なども「ピウス」の尊称を授かりましたが、通常「ピウス」といえば、ローマ五賢帝の一人 アントニヌス・ピウス帝を指します。
彼はAD86年に政治家の息子として生まれました。祖父と父は執政官を務めた富豪であり、恵まれた環境で育ちました。元老院議員、財務官、法務官、執政官など、ローマ政治の中枢で要職を歴任し、属州の総督も経験しました。
AD138年、当時のハドリアヌス帝の養子となり、「副帝」として事実上の帝位継承者となります。
実際には、ハドリアヌス帝はマルクス・アウレリウスを後継者としたかったようですが、マルクスがまだ若すぎるということもあり、行政経験豊富で人格者として知られたアントニヌスを後継に指名したのです。尚、その後をマルクス・アウレリウスに継がせることもこの時から決まっていました。
「高潔」『謙虚」という言葉がぴったりのアントニヌスは、皇帝に即位してもその姿勢を曲げることはありませんでした。元老院や軍との関係にも気を配り、持てる莫大な富を市民に還元することを忘れませんでした。贅沢に溺れることはなく、素朴で静かな生活を好み、公私を混同させることは無く振る舞いました。彼は国庫の金を自らのために使うことはせず、極力自分の私財から支出しました。
謙虚で相手を敬う気持ちを持ち続けた皇帝はあらゆる人々から幅広い支持を受け、まさに「聖人君子」という言葉がよく似合う治世を実現します。トラヤヌス帝や先代のハドリアヌス帝が独断・強行型の強い指導者であったのとは対照的に、アントニヌス・ピウス帝は合意形成を重視する協調型の指導者でした。

アフリカ属州(現在のチュニジア)の中心都市カルタゴに建設された大型公衆浴場。巨大なサウナ室もあり、地中海に面した風光明媚な立地に建てられた。
アントニヌス・ピウス帝の治世下に建設され、通称「アントニヌス浴場」の名で呼ばれた。
トラヤヌス帝時代に領域を最大化し、ハドリアヌス帝によって防御強固なものとしたローマ帝国は、空前の平和と繁栄の時代を迎えました。いつしか当時のローマ人は「黄金世紀」、後世の人々からは「パクス・ロマーナ」と呼ばれる時代の到来です。ローマにとって幸運であったのは、この絶頂の時代にトップに君臨したのが暴君や暗君、浪費家ではなく、高潔で人徳にあふれ、人望を大いに集めることの出来た大人物であったということでしょう。
アントニヌス・ピウス帝時代は周辺諸国との紛争も少なく、皇帝は首都ローマから離れることなく広大な帝国の統治を行えました。行政機関が確立されていた、平和な時代のローマ帝国ならではといえるでしょう。また、周辺諸国との対立が起こりそうな場合も、アントニヌス・ピウス帝は相手国に直接書簡を出し、平和的に収めさせたといわれています。
アントニヌス・ピウス帝は即位時に52歳であり、当時のローマ人から見れば既に高齢でしたが、彼の治世は23年に及びました。平和な時代で皇帝自ら外征に赴くことも無く、また本人も規律正しい穏やかな生活を送っていたことから、長寿を実現できたのです。
彼は23年にもわたる在世中、大きな改革や変更を行わず、また大事件や戦役も起こりませんでした。皇帝自身の人柄や人間関係も良好であり、個人的なスキャンダルとも無縁でした。欲望や人間味溢れるドラマテックなローマ帝国史にあって、あまりにも完璧すぎ、特筆すべきことの無いアントニヌス・ピウス帝の治世は異例中の異例でした。後世の歴史家は、彼に「歴史無き皇帝」という評価を下したほどでしたが、それは決して批判的評価ではなく、むしろ戦争や虐殺で彩られたローマの歴史にあっては最大限の賛辞といっても差し支えないでしょう。

ローマの神々に祝福されながら天に召されるアントニヌス・ピウス帝と皇后ファウスティナ。アントニヌス・ピウス帝亡き後に作られました。
平和と秩序を愛し、繁栄した治世を実現させたアントニヌス・ピウス帝時代のコインは、皇帝の財政健全化政策もあって金性や価値が安定していました。治世中、数多くの尊称を元老院から贈られた皇帝は、コイン上の自らの肖像周囲部に細かくその称号を刻みました。
デザインとしては、他の皇帝と同じく表面に月桂冠を戴く皇帝の肖像が打たれています。アントニヌス・ピウス帝のコイン肖像の特徴は、面長で豊かな髭を蓄えた皇帝が、上目遣いで表現されている点です。また、その鼻は高く、教養溢れる落ち着いた紳士の風を醸し出しています。
美男としても知られた皇帝の謙虚な人柄を巧く表現した彫刻になっています。なお、コイン肖像では首が非常に長く表現されているのも特徴です。目元は他の皇帝のように力強いものではなく、目尻が下がったように表現されています。ここからは裏面も合わせて、代表的なコインをご紹介します。
表面にはアントニヌス・ピウス帝の肖像。
裏面には「握手」の図。これは皇帝とローマ軍団との信頼・友好関係を示しているとされます。
裏面は平和の女神 パックスの立像。平和を尊び、安定した治世をローマに実現させた、アントニヌス・ピウス帝の信条を明確に表しています。立像の下部には、「PAX」の刻銘。
裏面には希望の女神 スペースの立像。女神を挟むように打たれた「S/C」の刻銘は、「元老院決議に基づく」のラテン語略銘です。当時、銀貨と金貨の発行権限は皇帝に属していましたが、銅貨の発行に関しては元老院の管轄でした。
裏面は神祇官のトーガを身に纏ったアントニヌス・ピウス帝自身の立像。アントニヌス・ピウス帝は武人として表現されるより、文官、神官としてコインに表現される例が多く見られます。同様のデザインは、デナリウス銀貨にも打たれました。
表面 上目遣いのアントニヌス・ピウス帝の肖像周囲部には、「国父にして護民官権限を持つ皇帝アントニヌス・ピウス 執政官三回目」との銘文がある。
裏面には最高神 ユピテル(ジュピター)の立像。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
次回も宜しくお願いします。
こんにちは。
本日は、代表的なギリシャコインについての記事をご紹介させていただきます。
今回はロードス島 ヘリオス神のコインの紹介です。
ギリシャ神話に登場するヘリオス神は、クァドリガ(四頭立て戦馬車)に乗って天空を駆ける「太陽神」として描かれています。ヘリオス神はローマ神話では「ソル」の名で知られるようになり、ソル(Sol)はやがてラテン語圏で「太陽」を意味するようになります。
ヘリオス神は長髪の若い美男子として表現されることが多く、その頭には太陽神としての光明を表す「光の冠」が乗せられた姿である場合が多く見受けられます。また、ヘリオスの聖鳥は朝の到来を告げる「雄鶏」とされました。

ヘリオス神のクァドリガは太陽をひくと考えられ、それが周期的に天空を駆け巡ることから、一日の間に朝・昼・夜と変化すると考えられました。尚、ヘリオス神のクァドリガの後ろには、月の女神セレーネがついてゆくとも捉えられ、天空の動きを説明する要素のひとつになりました。
彼の息子にパエトンという人物がいます。彼は父親のクァドリガを借りて、自らが太陽を率いようとしましたが、初めての運転は上手くゆかず、やがて地上へ向かって走り出させてしまいした。太陽が近づき過ぎた地上は草木や農作物が枯れ、水は干上がりそうになります。そこで大神ゼウスは自らの雷をパエトンに放ち、パエトンを殺して太陽を天空へ戻したとされます。
(※伝承によっては、サハラ砂漠ができたのも、アフリカ人の肌が黒くなったのもパエトンが太陽を地上に近づけさせた為、と説明されることもあります。)

暴れ狂い、混乱する馬車はヘリオス神のクァドリガ
さて、ヘリオス神とロードス島の関連ですが、ロードス島には「ロードスは太陽神ヘリオスに捧げられた島」という伝承があり、島の各所でヘリオス神を祀っていたと考えられています。
最も有名な逸話では、世界七不思議の一つに数えられる「ロードス島の巨像」です。
ヘレニズム時代、亡きアレキサンダー大王(マケドニア王アレクサンドロス3世)の部下達は後継者戦争を東地中海各地で繰り広げました。エーゲ海に南部に位置したロードス島は海運で栄え、アナトリア(現在のトルコ)にも近いことから、軍事的な要衝でもありました。
この戦争中、ロードス島はプトレマイオス陣営に付き、対岸のアナトリアを支配したアンティゴノスの軍を牽制するのに活躍しました。後にプトレマイオスが興したプトレマイオス朝エジプトはこの功績を称え、ロードス島の庇護者となり、海運業を保護して繁栄を約束したとされます。
アンティゴノスとの戦いに勝利したロードス島民は、この勝利を守護神ヘリオスのおかげとして、戦勝記念の巨大なヘリオス像を建設しました。これが後に「ロードス島の巨像」と呼ばれることになるヘリオス像です。


(画像は後世の想像図。その具体的な姿は未だ不明である。)
ヘリオス像は海運の中心地であるロードス港に建てられた高さ50メートルにもなる巨大なブロンズ像であったと考えられています。ヘリオス像の持つ松明は夜になると火が灯され、灯台の役割も果たしたといわれています。
BC284年に完成したこの像は、地中海世界の代表的名所として、当時の記述にも多く登場しました。海運業で港に停泊した船の乗組員は、ロードスの港で目にした巨大な像の話を、誇張を交えながら目的地やふるさとで話したと思われます。
一大観光名所となった巨像ですが、BC226年の巨大地震で倒壊。当時のエジプト王プトレマイオス3世は再建を申し出るも、島民は「大き過ぎる像を建てた人間達に対するヘリオス神の怒り」によって像は倒壊したのだと考えて申し出を断り、二度と再建されることはありませんでした。
土台や残骸は長らく放置され、それも一種の観光地となりましたが、後にロードス島を占領したイスラーム教徒の軍団、ウマイヤ朝軍によって跡形もなく持ち去られたといいます。
紀元前3世紀に存在した超巨大な像は、もはや伝承によってしかその存在を確認できず、姿かたちを全く留めていないことから「世界七不思議」の一つとされました。
表面にはヘリオス神。裏面には四角陰刻内のバラ。
そのロードス島で造られた古代コインの多くは、そのほとんどにヘリオスの肖像が表現されています。表面にはロードス島の守護神ヘリオスの肖像、裏面にはバラの花が打たれています。
かつて、ロードス島がヘリオス神に捧げられた際、その島には美しいバラの花が咲き乱れており、ヘリオス神はこの島を大層気に入ったという伝承に由来するデザインです。今でもロードス島は「太陽とバラの島」と称され、風光明媚なエーゲ海の島として人気が有ります。
ロードス島とヘリオス、バラの関係性は諸説あり、その由来は定かではありませんが、少なくとも現存するコインを見る限り、「ヘリオス」と「バラ」が古代のロードス人にとって重要なモティーフなっていたことは間違いありません。全時代を通してみても、「ヘリオス/バラ」の組み合わせ自体は長く継承されていたことが分かります。
コイン上のヘリオスは横顔だけでなく正面を向いたもの、斜め前を向いたもの、光の冠を被ったものとそうでないものなど、バラエティに富んでいます。裏面のバラも、小さな葡萄房が入ったものや太陽が入ったものなどが確認されており、一応に「ヘリオス神/バラ」といってもバラエティに富んでいます。
これはギリシャ・ローマコイン全般に言えることですが、同じ組み合わせのモティーフであっても、造られた時代や彫刻師の個人差によって趣向が大きことなります。そこが古代コインの面白さでもあります。
光の冠を戴くヘリオス神。裏面はバラの花と小さな太陽。
斜め前を向いたヘリオス神。光の冠は被っていない。
裏面にはバラと共に葡萄の房が表現されている。
表面はヘリオス神の横顔。裏面は四角ではなく、円に縁取られた囲いの中にあるバラの花。
長髪を逆立たせ、斜め前を向くヘリオス神。裏面は縁が全く無いバラの花。
光の冠を被ったヘリオス神の横顔。裏はバラの花と共にカデュケウス(伝令の杖。ヘルメス神の持物)が打たれている。
様々なタイプがあるヘリオス/バラのコインですが、時代が下がってゆくとマケドニアなどの地域でも、ロードス島のコインを模倣したような「ヘリオス/バラ」のコインが造られました。
エーゲ海の要衝であり、東地中海交易の中心地のひとつであったロードスのコインは島内に留まらず、交易で立ち寄った船に乗ってギリシャやエジプトなど、東地中海各地へ旅したと考えられます。
余談ですが、時代が下がって中世の時代、ヨーロッパのある小さな教会で、「ユダがイエスを裏切った際に得たシュケル銀貨」として大切に納められていた銀貨は、なぜかロードス島のヘリオス神が描かれた銀貨だった、という逸話が残っています。
(※ローマ帝国時代初期のパレスティナでは、皇帝の肖像を刻んだデナリウス銀貨が流通しており、ユダの受け取った銀貨30枚もデナリウス銀貨だったと考えられる。)
お読みいただき、ありがとうございます。
次回も宜しくお願いします。
こんにちは。
だいぶ涼しくなり、すっかり秋らしい日も多くなってまいりました。
さて、前回はギリシャコインに関する記事をご紹介したので、今回は古代ローマコインに関する話題をご紹介します。
古代ローマコインは大きく「共和政時代」と「帝政時代」に分けられます。
共和政時代のコイン様式はギリシャコインと似ており、神話に登場する神々の姿が表現されています。
ローマ共和政時代のデナリウス銀貨に表現された代表的な神は「ローマ神」です。
ローマ神は都市国家であったローマの守護女神であり、その姿は翼の付いた兜を被った横顔が表現されていました。細かく見ると、イヤリングなどの装飾も刻まれており、女神であることが分かります。
共和政時代を通して長く表現されたローマ神は、共和政ローマそのものを具現化した存在であったと考えられます。
(写真はBC111年頃のデナリウス銀貨)
一方、帝政時代のコインは、その時々のローマ皇帝の肖像が表現されているという特徴があります。共和政時代の末、ローマの実質的な独裁者となったユリウス・カエサルが自らの肖像をコインに表現させて以降、オクタヴィアヌスやマルクス・アントニウスなど、実在の人物がコイン上に表現されるようになりました。長年、共和政を国是としていたローマのシステムが行き詰まり、強力な指導者の登場を時代が求めた故の現象といえます。
BC27年、オクタヴィアヌスは元老院より「アウグストゥス(尊厳者)」の尊称を授けられ、これをもってローマの帝政時代の開始とされます。以後、初代皇帝アウグストゥスの時代から5世紀の西ローマ帝国滅亡まで、イタリア半島で発行されたコインには皇帝の肖像が打たれるようになったのです。
(写真は皇帝に即位する前のオクタヴィアヌスを表現したデナリウス銀貨[BC32年])
コインにはその時々の皇帝だけでなく、皇妃や副帝といった皇族の肖像も打たれ、その人物が当時、ローマ帝国の中央政界でいかに大きな影響力を持っていたのかが伺えます。
五賢帝の一人、マルクス・アウレリウス帝の副帝時代に発行されたデナリウス銀貨。トレードマークの豊かな髭が無い若者の姿。(AD140年発行)
アントニヌス・ピウス帝の皇妃ファウスティナを表現したデナリウス銀貨。
AD140年に崩御したファウスティナ妃は、死後にローマ元老院によって「神」に列せられた。この銀貨はAD145年に発行されたもの。
15世紀末にイタリアを中心に興った古代文化・文芸復興運動「ルネサンス」の時期には、帝政時代のローマコインを体系的にまとめて研究し、そこからローマ時代の歴史、政治、文化を明らかにする取り組みが試みられました。コイン上に刻まれた皇帝の肖像と銘文を手掛かりに、その時代の政策や歴史的事件、信仰を解き明かそうとしたのです。
歴代のローマ皇帝の肖像を刻んだコインは、イタリアやドイツ、フランスの文化人や王侯貴族を魅了しました。貴族や王侯は出入りの骨董商にローマ時代のコインを見つけさせては、屋敷や宮殿の宝物庫に納めさせました。書斎や図書室の引き出しに収納できる、小さな古代ローマ帝国の遺物は、ルネサンス時代を生きた人々を古代のロマン溢れる世界へ誘ったのです。
当時の王や貴族、富裕な商人や文化人も、現代の我々と同じように夜な夜な一人書斎に篭ってコレクションを眺め、それらが実際に使用されていた古代の世界に想いを馳せていたことでしょう。
また、歴史的にヨーロッパの王侯貴族は、子弟の帝王学教育、歴史教育の教材としてもローマコインを用いました。ルネサンス時代に起こった古代コイン収集熱は、今のコインコレクション市場の基礎となったのです。
神聖ローマ帝国皇帝でありスペイン王であったカール5世(皇帝在位:1519年~1556年)も、熱心なコインコレクターの一人でした。宮廷に出入りするイタリア人商人に注文し、イタリアで発掘された古代遺跡から出土した珍しいコインをドイツまで送らせました。
このイタリア⇒ドイツへの古代ローマコイン供給によって、ドイツにはローマコインが多く流れ込み、コイン収集・研究の土台ができました。現代でもフランクフルトやミュンヘンでは、古代ローマコインが盛んに取引されています。

(神聖ローマ帝国皇帝在位:1519年~1556年、スペイン王としては「カルロス1世」 在位:1516年~1556年)
また、近現代では、イタリア王 ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世(在位:1900年~1946年)も古代コインに魅了された王の一人であり、彼に至ってはコイン研究書まで著しています。
さらにコイン発行の最高権限者でもある自らの地位を最大限活用し、イタリア本国と植民地で多種多様なデザインのコインを発行したことでもしられます。その多くは、古代ギリシャ・ローマのコインからインスピレーションを受けたと思われるデザインが多くを占めています。
自らが理想とする芸術的なコインを実際に造り、それを公的に発行してしまうのは職権乱用のような感じもしますが、それらのコインは収集家の人気の的となり、現在でも市場で高値で取引されています。
国王は第一次世界大戦とファシストの台頭、第二次世界大戦の敗北に伴う王国の消滅を経験し、失意のうちに亡命先で亡くなりました。20世紀前半の世界情勢に翻弄された、苦労の多い君主でしたが、彼の作品とも言えるコイン達が今も尚、世界中のコインコレクターを魅了し、垂涎の的となりえていることを考えれば、コインコレクター冥利に尽きるといったところではないでしょうか。
1914年発行の2リラ銀貨。肖像はヴィットーリオ・エマヌエーレ3世。
裏面には四頭立て馬戦車を操るミネルヴァ女神が美しく表現されています。彫刻法や製造法は近代的ですが、裏面の構図はローマ共和政時代のデナリウス銀貨裏面と類似しています。
三頭立て馬戦車(トリガ)を操るヴィクトリー女神が表現されています。この構図はローマ共和政時代のデナリウス貨裏面に多くみられました。馬戦車がビガ(二頭立て)であったり、または山羊であるなど、多様な種類が存在します。馬戦車を操る神も様々です。
さて、話題をローマコインそのものに戻しましょう。
ローマ時代のコインがローマ帝国史を知るうえで重要な史料となると考えられたのは、コイン上に表現された歴代のローマ皇帝達の肖像は、今は亡き本人の顔つきと性格を巧みに表現していると考えられるからです。
ネロ帝の二重あごから、ウェスパシアヌス帝とティトゥス帝の親子がみせる、よく似た頑固そうな顔つき、ネルヴァ帝の鷲鼻からユリアヌス帝の豊かな哲学者風山羊顎髭まで、歴代皇帝達の個性あふれる風貌を時に大げさに、時に写実的に表現しています。
ネルヴァ帝(AD97年) ユリアヌス帝(AD361年-AD363年)
日本では明治時代に入るまで、一般民衆は天皇や将軍の顔を知ることなく一生を終えていたことを考えると、大変興味深い文化の差だといえます。
しかし帝政後期に入ると、初期キリスト教主義の影響から写実性はあまり重視されなくなり、形骸的な無個性の肖像が多く用いられるようになります。時代が下るより、むしろ帝政時代の初期の方が、顔だけで皇帝を判別することが容易なのです。
現代の我々が見ても、コインの肖像を見ただけでどの時代のローマ皇帝かを判別することは容易です。コインに打たれた肖像は、現存する皇帝の胸像と極めてよく似ているからです。
ただ、皇帝によっては自らの肖像を修正させ、理想的な姿を打った例も見られます。最も顕著なのは初代アウグストゥス帝(在位:BC27年~AD14年)です。
アウグストゥスは威厳に満ちた自らの肖像を、ローマ帝国に住む多くの住民に知らしめることに腐心しました。
アウグストゥスの妻リウィアが所有していたプリマ・ポルタの別荘に置かれていたアウグストゥスの立像は、威厳に満ちた最高権力者であり、勝利者の彫像です。
発掘された際は既に白色だったが、当時は着色されていたことが判明している。
これら彫像は多くコピーされ、ローマ市内をはじめ帝国各地の公の場に立てられました。アウグストゥスの公的なイメージを広める意味でそれ以上に重要な役割を担ったのが、経済流通で人から人の手に、広い大帝国内を無限に渡り歩く媒体「コイン」でした。
BC2年~AD12年に発行されたアウグストゥス帝のデナリウス銀貨。
治世初期の肖像は共和政時代末と同じく無冠でしたが、政権が安定すると勝利者の証である「月桂冠」を戴いた端整な顔立ちの肖像を表現させました。
この様式はその後も継承され、コインに表現されるローマ皇帝の肖像は月桂冠を戴いたものが標準と成りました。
ローマ帝国時代のコインは支配者たる皇帝の顔を、帝国に住む末端の民に至るまで広く知らしめる役割が期待されていました。そのため、皇帝は自らの政治信条や戦場での勝利を、肖像の裏面に寓意的なモティーフとして打たせたのです。今では、その特徴的モティーフと当時の文献史料とをすり合わせることで、そのコインがいつごろ造られたのかを特定することができるのです。
本日はここまでとさせていただきます。
次回もお楽しみに。
こんにちは。
ご無沙汰しておりました。
すっかり更新が滞ってしまい、誠に申し訳ありません。
今回から、また定期的に、少しずつではありますが、ブログを更新していきたいと思います。
さて、今回からは、古代ギリシャ・ローマコインに関する情報を発信していきたいと思います。
毎回、古代ギリシャ・ローマの代表的なコインを紹介し、そのコインに関することをお伝えします。
今回は、古代ギリシャの代表的コインであるアレキサンダーコインをご紹介します。
アレクサンドロス3世(アレキサンダー大王)は、BC336年からBC323年まで在位した古代マケドニア王国の若き王です。彼は少年時代より数々の武勇を誇り、その存在は当時から生ける伝説として知られました。
父王フィリッポス2世亡き後、父の領土拡大路線を引き継いだ20歳のアレキサンダー大王は、ギリシャ全土に留まらず、小アジア(現在のトルコ)、シリア、エジプトへ遠征し、広大な領土を我がものとします。
エジプトで「ファラオ」の地位を得たアレキサンダーは、長年ギリシャ世界の脅威であったペルシアへ遠征し、これを征服しました。さらにそれでは飽き足らない大王は、中央アジアを経てインドへの遠征を行いますが、部下の疲労や自身の体調不良から侵攻を諦め、ギリシャへと帰還する途上で亡くなりました。
32歳という若さでしたが、彼が戦いに明け暮れた12年の間に帝国はかつて無いほどの広がりをみせ、ギリシャ世界と東方文明の融合という「ヘレニズム時代」を築きました。
征服地には、部下を入植させて現地人女性との結婚を奨励しました。そうして築かれた都市は、大王の名から「アレクサンドリア」と呼ばれるようになり、現在残る地名ではエジプトのアレクサンドリアが最も有名です。

さて、ここで取り上げるアレキサンダーコインとは、通常ヘラクレスの肖像が表現されたテトラドラクマ銀貨を指します。テトラドラクマの「テトラ」とは、古代ギリシャ語で「4」を示し、ドラクマ銀貨4枚に相当した大型銀貨です。
アレキサンダー大王時代より以前から、テトラドラクマ銀貨はギリシャ諸都市で発行され続けていましたが、重量はほぼ等しいものの、そのデザインは各都市によって異なりました。
当時のテトラドラクマ銀貨は日常的に使われていたコインではなく、交易や戦争、神殿建設など大規模な出費が伴う際に、対外決済用として発行されていたものでした。
アレキサンダー大王は、自らが征服した地域内の交易が円滑に進むように、また、東方遠征の戦費を調達するために統一されたデザインのテトラドラクマを発行させました。
表面にはヘラクレスの肖像が、裏面にはギリシャ神話の最高神ゼウスの坐像が表現されています。ゼウス神は右手にゼウスの聖鳥である大鷲を休ませています。ゼウス坐像の右側には、古代ギリシャ語で「アレクサンドロス」を示す「AΛEΞANΔPOY」の名が刻まれています。
この組み合わせのモティーフは、ドラクマ銀貨など、他のコインにも用いられました。
アレキサンダー大王は生前より、自身をギリシャ神話の英雄ヘラクレスの末裔と自称していました。
ヘラクレスはゼウスの子であり、神の力を備えた猛々しい英雄として、当時のギリシャ男児の憧れの存在でした。北方のマケドニア王国は、当時のギリシャ人からは周辺に住む「蛮族」と見做されていたため、ギリシャ地域で権威を持たせる意味合いもあったのです。
この銀貨に表現されたヘラクレスのモデルは、アレキサンダー大王本人であったと考えられています。
当時のギリシャ諸都市で発行されたコインには、存命中の人物が表現されることは無く、多くはギリシャ神話の神や女神でした。アレキサンダー大王もそれに従い、文字通り表面上は「ヘラクレス」として表現させましたが、実際はライオンの皮を被った自らの肖像を打たせ、自身の権威が神に並ぶものとして示したと考えられます。
当時のギリシャ人やマケドニア人は、武功のある軍人や王に対しては「優れた指導者」と見做していました。一方、エジプトやペルシアなどのオリエント諸国では、王は「神に近しい存在」と考えられていました。
オリエント諸国を征服し、自らの大帝国を夢見る大王にとっては、ギリシャ風の「機能的な指導者」像よりも、エジプトやペルシアのように強く、神聖不可侵な帝王像が魅力的だったのです。
アレキサンダー大王が亡き後、大王の後継者達が各地で発行したコインをみると、アレキサンダーが自身を「神」に見立てていたことがよく分かります。後継者達は亡き大王の権威と名声を最大限活用し、自らの正統性をアピールしました。その過程で、大王の神格化がコイン上でも進められていたのです。
その為、従来のヘラクレススタイル以外の肖像でも、数多くのアレキサンダーコインが造られました。
プトレマイオス朝エジプトをはじめとするいくつかの地域では、角の生えたアレキサンダーの肖像をコインに表現しました。これはエジプト遠征の際、アレキサンダー大王本人が現地の神官より、「大王はアモン神の生まれ変わり」との神託を受けたことに由来しています。
(この銀貨は大王の死後、トラキアで発行されたもの)
また、東方に遠征し、最終的にインド征服を企てていた大王の姿は、象の皮を被ったスタイルでもコインに表現されています。
当時、象は戦闘において「戦車」の役割も果たしました。敵方を威圧し、戦意を喪失させるには大変効果的であったと思われます。象皮の頭巾は言わば武功、武勇の象徴でもありました。
(大王の死後、エジプトで発行されたもの)

大王が亡くなった後も200年以上の長きに渡り、地中海を中心として多くのアレキサンダーコインが各地で発行されました。それはかつて大王が示した経済的、軍事的威光が、後世まで広い地域に影響を与え続けていたことの証でもあります。
長い年月、地中海各地で造られ続けたアレキサンダー大王のコインは、「ヘラクレス/ゼウス神坐像」という基本的なスタイルを保ちながらも、各時代、地域の彫刻師による個人差が表されています。同じテーマを与えられても、描く人によって差異が出るのと同じように、アレキサンダーコインは当時の人々や地域の持つ技術力や美意識が反映されています。
古代コインコレクションを行うにあたって、多種多様なアレキサンダーコインの中から「これは!」と目に付いたものがあれば、それはその人の感性と、そのコインが造られた時代、地域、造った彫刻師の感性が見事にシンクロした瞬間といえるでしょう。古代に生きた人々と現代を生きる人々をつなぐところに、古代コインのロマンがあると感じます。
アレキサンダーコインの面白味は、そういったところに感じられる「感性の個人差」でもあります。
アレキサンダーコインに関するお話は尽きることがなく、アレキサンダーコインのみについて書かれた専門書も存在するほどですが、ここでは割愛させていただきます。
今回はこの辺で。
次回からも、代表的な古代ギリシャ・ローマコインの紹介をさせて頂きます。
投稿情報: 14:53 カテゴリー: Ⅱ コイン&コインジュエリー, Ⅲ ギリシャ | 個別ページ | コメント (0)
初期のローマ世界では、アフリカの遊牧民と同じように家畜が家の財産としてみなされていた。
物々交換が経済活動であった時代、家畜は特に有効な交換単位の一つだった。
その後、秤量貨幣(アエス・ルデ)と呼ばれる延べ棒のような貨幣が登場した。この貨幣には当初、物々交換時代の名残から牛などの家畜が刻印されていた。
秤量貨幣はその重さが規格化されていたとはいえ、最大重量が約1.6kgもある、絵柄付きの延べ棒であった。
その後、ギリシャを倣って円形のものも作られたが、あまりに重すぎるそうした貨幣は扱いやすい通貨とは言えず、広く流通することはなかった。後世のラテン語表現の中には、金銭の支払いに関して「gravis(重い)」という表現が存在する (例:重い罰金) が、それは実際に「重い貨幣」を使用していたことに由来している。
現在のコインに近い貨幣がローマに登場するのは、紀元前300年頃であると考えられている。この頃からローマは、カンパーニア(イタリア半島南部)に存在したギリシャの造幣所に青銅貨や銀貨等のコインの鋳造を委託している。
当初は自国での鋳造を行わず、当時のコイン先進地域であったギリシャにコイン鋳造を委ねていたのである。
その後、ローマで初めて貨幣の鋳造が行われたのは紀元前269年といわれている。
古代ローマの通貨体系の基本単位は、帝政期に至るまで約4gのデナリウス銀貨であった。デナリウスは紀元前200年頃から銅貨(アス)12枚に細分化された。

ユリウス・カエサル時代に鋳造されたデナリウス銀貨であり、表面には農耕神セレス、裏面には壺や杖等が刻印されている。
紀元前89年以降、デナリウス銀貨とアス銅貨の交換比は1:16であった。銀貨と銅貨の間にはセステルティウス貨が存在した。
紀元前216年には金貨の発行が開始された。しかし共和政時代、金貨の発行はさほど多くなく、全体量から考察すると少数だったとみられている。

重量は1.03gと超小型である。表面にはローマ神、裏面には双子神ディオスクリが刻印されている。
アウグストゥス帝の時代、アウレウス金貨の価値は25デナリウス銀貨に確定した。
以下はユリウス=クラウディウス朝時代(紀元前31年~紀元68年)のローマ帝国通貨とその相対的価値である。
尚、「アウレウス」とはラテン語で「金」を意味する。
尚、3世紀になると急激なインフレーションが発生し、デナリウス銀貨の銀含率は著しく低下した。以降、ローマ通貨の中心単位はアウレウス金貨になった。
直径19㎜で量目7.79gの帝政ローマ初期の金貨。写真の肖像はティベリウス帝(在位:14年~37年)。裏面にはリウィア坐像が刻印されている。
しかし、庶民の日常の中で銀貨や金貨が登場する機会は少なかった。多くの市民は日常生活において、最も身近なコインとしてはアス銅貨を使用していたからである。

写真の銅貨表面肖像はアグリッパ(カリギュラ帝の祖父)、裏面の立像は海神ネプチューンである。この銅貨はカリギュラ帝の治世下(37年~41年)で発行された。
富裕層は金貨や銀貨を自宅の金庫に貯め込んでいた。
当時、有産階級の富裕世帯には必ず青銅製、または鉄製の金庫が存在した。金貨、銀貨等の蓄財は人一人が入れる位の鉄製の鍵がついた金庫にしまい込まれ、必要な出費の毎にそこから支払われていた。金貨や品質の良い銀貨(特に1世紀~3世紀初頭のもの)は一般の流通市場には乗らず、資産保護のために大屋敷の金庫の中にしまい込まれていたのである。
しかし、このことによって多くのローマ金貨、銀貨が良い状態で保存され、後世のコインコレクター市場向けに多くのコインが残されたのである。
ローマ帝国時代には物流も交通網も発達し、貨幣は経済活動の根源となっていた。いかなる階層に属する者であっても、貨幣によって生計を営んでいたのである。労働者の報酬も、現金による賃金が基本化していた。
日々の買い物はもちろん、宿から娼家に至るまで、貨幣による支払いが唯一の決済手段だった。

ローマ帝国では貨幣経済が末端にまで浸透しており、大都市ローマから地方、属州に至るまで支払いには時の皇帝の肖像が刻まれたコインが日常的に使用された。
ローマ帝国内に暮らす者にとって、コインは生きていく上で欠かせないものうぇすぱしだったのである。
広大な帝国の各地にコインを供給する為、ローマをはじめ属州にも造幣所が設置された。後期には帝国各地20か所に造幣所が存在した他、ギリシャや小アジア(現在のトルコ)の自治都市では、当地のみでの流通に限られていたが、独自貨幣の鋳造も認められていた。
さらに、紀元前2世紀以降、記念コインの発行が頻繁に行われるようになった。記念コインは既にこの頃から存在していたのである。
紀元前46年~紀元前45年の発行。勝利のトロフィーを中心に据え、両脇に二人の捕虜を描いている。
広大な帝国全土にローマ皇帝の権威を誇示する為、貨幣という効果的な流通媒体に政治的スローガンやモットー (例:felicitas(幸福)、liberalitas(自由)、concordia(協調)、justitia(公正)等・・・) を刻むことが流行した。
皇帝の対外戦勝記念や文化事業記念も、コイン上に刻まれたことで威厳を高めた。
そして、後世(特にルネサンス期の西欧)にはそうした記念コインが、古代ローマ史研究の一助にもなったのである。
当時から納税も現金(コイン)で行われていた。相続税、人頭税、地税等、ローマ市民から属州民まで、幅広い帝国臣民が様々な課税の対象となっていた。
イエス・キリストはユダヤの律法学者に「ローマ皇帝に重い税を納めなければならないか?」と問われた際、デナリウス銀貨に描かれたローマ皇帝の肖像を指摘し、「神のものは神に、皇帝のものは皇帝に返せ」と答えたという逸話が聖書にも残っている。
このことは、当時から辺境の属州にまでローマの貨幣制度と、そこに描かれた皇帝の権威が及んでいたことの証でもある。通貨とそれを発行、流通させる国家権力とは密接な結びつきを帯びており、なおかつ末端の庶民にまで影響をおよぼしていたのである。
強欲でケチな皇帝として知られたウェスパシアヌス帝(在位:69年~79年)は、財政再建の為に増税を行ったが、その中でも印象が強いのは通称「尿税」である。当時、尿は毛織物の染色や皮なめし、洗濯に使用されていたことから、公衆便所の尿にまで税金をかけたのである。
この税によって、当時から後世に至るまで「ウェスパシアヌス帝=ケチ、強欲」という評価が下されることになった。
左は75年のデナリウス銀貨、右は80年のデナリウス銀貨
息子のティトゥス(次帝 在位:79年~81年)は父帝に対し、尿税はローマ皇帝の権威と尊厳を損なうものであるとして抗議した。
すると父であるウェスパシアヌス帝は、この税によって徴収した金貨を息子に嗅がせ、臭いかどうか尋ねたという。
本日は以上となります。
お付き合い下さり、ありがとうございます。
次回も宜しくお願い致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コインペンダント専門店 『World Coin Gallery』
よろしければクリックお願いします。
こんにちは。
いよいよ1月も最後となりました。
まだまだ寒い日々は続いていますが、2月に向けて頑張りましょう。
さて、本日のブログ記事は、先週に引き続き古代ローマ人の日常に関しての知識をお伝えします。
近頃は寒い日が続いて、家の中の掃除や冷たい水を使う家事が億劫になっていませんか?
と、いうことで今週のテーマは、古代ローマ人の「家事」についてです。
古代ローマ人の日常では、家庭内での家事はどのように捉えられていたのでしょうか?
また、古代ローマの「主婦」とはどのようなものだったのか?
今回は「家事」というキーワードを基にして、古代ローマ人の日常を御紹介したいと思います。
古代ローマにおける家庭内の仕事とはいかなるものであったのか?
現代の感覚から捉えれば、掃除、料理、洗濯、ベッドメイキング等がまず思い浮かぶ。
しかし、これらは現存する資料からはまず分からないし、そもそも中流階級以上の主婦はこのような仕事を行うことはなかっただろうと考えられている。
というのも、これらは典型的な奴隷の仕事であったからである。
大きな世帯では、一部は専門の使用人が、中流家庭では1人~3人の奴隷が家庭内の家事をこなしていたと考えれている。
このような家事を調整し監督するのは、もちろん一家の主婦の責任であった。
「家を守る」ことは、夫と妻の古典的分業の範囲内では、当然主婦に帰属すべき管理機能であった。つまり、古代ローマの社会では、家庭内の雑務の有無に関わらず、ほとんどすべての家政は主婦の担当であると考えられていたのである。
一方で、豪邸に住まう一族や地方で荘園を経営するような階級に属した多くの主婦は、その監督義務をも「ウィーリカ」と呼ばれる不自由身分(奴隷)の女管理人に委ねることが多くみられた。特に大きな屋敷ではそうした伝統が代々引き継がれ、農園を管理する不自由身分の管理人の妻が、その家庭の他の奴隷たちの家事を監督していた。
つまり、多くの使用人たちをまとめるチームマネージャーのような存在であり、ヴィクトリア朝時代の英国にみられた「メイド長」のようなものである。
ウィーリカは住居を清潔に保ち、家人から使用人たちの食事にまで気を配っていたのみならず、大きな農場を有している屋敷では、果実の収穫、穀物挽き、家禽の世話等、夫の役割も補佐していた。
そのことから、郊外の大荘園主の妻は家事をほとんど行わなかったのではないかと推察される。
荘園を持たない都市の上流階級の大屋敷でも、多くの奴隷が使用人として存在していた。料理、掃除等の日常的な家事は、そうした奴隷たちが担当していた。
都市部の家庭でも、家事を女監督人に委ねることが多かったが、一般的には世帯主の妻自らが監督責任を担った。食事の作り方や掃除の仕方、日々のやるべきことを使用人たちに教え込み、また日頃からその働きぶりをチェックしていたのである。
また、妻は家計簿の管理も行い、家庭の金の出入りを厳しくチェックしていた。
この辺りは、現在の社会にも通ずるものがあるように感じられる。
しかし、大多数の一般的な市民の家庭には、奴隷などを抱えることは出来なかった。奴隷を使えない以上、当然 家事は家族が自らこなさなくてはならなかった。
家事の大部分は、ローマの社会に深く根差した役割の規範に基づいて、妻が受け持ってきたといえるだろう。 上流階級の妻や母に期待された役割は、ローマの社会全体で理想化され、それが無差別に社会の全階層に転用されていたようである。
加えて羊毛の加工作業は、中流階級以上の女性にとって模範的家事の一つとして認識されていたようである。 現在のように機械の並ぶ工場がない時代には、細かな手仕事で、しかも家庭の中で行えるとあって、女性向の仕事と捉えられていたのかもしれない。
事実、羊毛加工の仕事は、貴婦人に相応しい家事の一つとして長年讃えられてきた。
亡くなった妻を讃えたいと思う夫は、墓石の上に「貞潔」「優しさ」「従順」等の愛と感謝の言葉と並んで、当たり前のこととして羊毛加工の仕事(ラーニフィキウム)を刻ませたほどである。
都市部では乳母、女優、芸人、踊り子、売春婦等が女性の代表的な仕事であり、加えて小売業や織物業でも女性の姿が多くみられた。その中で家事も担っていたことを想像すると、家庭内での女性の負担は大きかったと思えてしまう。
ただ、ローマ等、都市部の住居の質素な調度とその量の少なさが、負担を軽くしてはくれていた。また、洗濯業では多くの男性従業員が働いていたことからも推測できるように、男性の洗濯屋が一般家庭の洗濯仕事を受け持っていた可能性もある。
料理に関しても、下層階級が住む「インスラ」と呼ばれた集合住宅には、住居に台所もかまどもなかったので、そもそも家庭内で料理ができないことが多かった。家に台所が無い人々が温かい食事を口にするには、ローマ市内の至る所にあった軽食堂を利用していたと思われる。
日常的に屋台や軽食堂を利用することで、あまり料理をしないという食生活は、現在の東南アジアの都市部でもみられる生活スタイルである。
軽食堂は道路上に出店された、いわば屋台であり、サービスカンターに加えて簡単な椅子とテーブルが路上に並んでいた。その為、帝政期のローマでは街中の交通の流れを滞らせ、多くの苦情も寄せられていたが、ローマ市内に住む庶民にとって、そこが唯一温かい食事を口にできる場所であった。
したがって、ローマ市内に住む女性が家事に費やした時間とエネルギーは、全体として見ても今日の一般的な量にはるかに及ばなかったといえるだろう。
しかしそれ以上に、型にはまった家事を「天職」だの心からやりたいことだのと感じた人はほとんど誰もいなかったと思われる。
しかし、「家を守る」という役割を期待された女性に対し、夫は様々な形で愛情と感謝を表したと思われる。「幸福な家庭」像は、現在と同じく古代ローマでも存在しており、男性にとってその理想と幸福を護ってくれる「家庭の天使」たる妻は、大切な存在だったのだ。
様々な文献、石碑には妻を思い慕う夫の想いが残されている。愛妻が亡くなった際、残された夫はその愛と感謝の気持ちを、妻の墓石に刻ませたのである。
それらの史料は、夫婦の愛情が古今東西不変であることを、現代の我々に物語っているのである。
最後に、かつて、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥス(在位:前27年~14年)が、妻リウィアに対して贈ったプロポーズの言葉を以下に御紹介する。

ローマ帝国初代皇帝。アウグストゥスはラテン語で「尊厳者」の意。
オクタウィアヌスは紀元前27年に同称号を受け、帝政が開始された。
写真は紀元前18年~紀元前16年にかけて鋳造されたデナリウス銀貨。
http://www.tiara-int.co.jp/detail.html?code=654281
カッシウス・ディオーン 『ローマ史』より
本日は以上となります。
皆様、御体にはくれぐれも気を付けて、新しい月を迎えましょう。
2月も宜しくお願いします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
コインペンダント専門店 『World Coin Gallery』
よろしければクリックお願いします。
投稿情報: 17:00 カテゴリー: Ⅰ 談話室, Ⅱ コイン&コインジュエリー, Ⅳ ローマ, Ⅶ えとせとら | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
最近のコメント